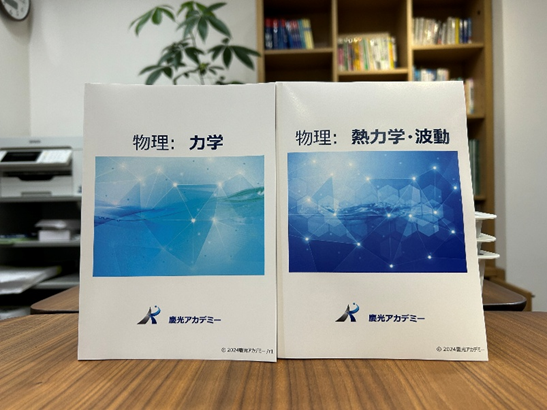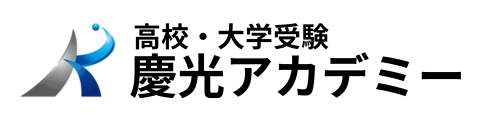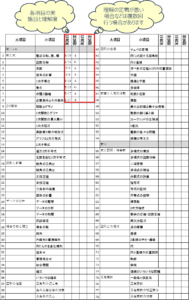私の大学受験を振り返ると、物理で非常に苦労したという思いがあります。ぶ厚い参考書2冊を行い、その後に難問を取り扱った問題集を行い、かなり遠回りしたという感があります。参考書をこなすということに気が囚われ、何が根底にあるのか、何が本質であるのかが分かれば、もう少しスマートにできたのではないかと思っていました。
そんな経験から、子供が大学受験に差し掛かった時に、物理の要点をプリントにまとめて説明した記憶があります。
“力学は物理の基本で、解くプロセスが非常に重要。物理学は未来を予測する学問であるから、単に値を求めるということに気を囚われるのではなく、物理的な数式を作成し、その式を使って横軸を時間軸にしたグラフを書くことで対象とするもののふるまいが分かる。物理の問題がそこまで要求していなくても、本当はそこまでやって(グラフ化して)物理としては完了する。 また、物理は数学の授業より1年ぐらい先の知識を必要とするが、その数学の知識を使用しない為に解法が分かりづらい場合がある。そんな時は、解く過程で物理の部分と数学の部分の切り分けをしっかりとするといい。極端な話、物理の法則にのっとった式を立てた時点で、物理の解答は終わり。(数学の知識がなくて、変な計算・解き方をするよりも、物理の式で留めた方がいい。。。)”と伝えたと思います。
電磁気では、色々な言葉や法則が出てきますが、それを力学で出てきた法則と対応させると、頭にスムーズに入りやすいと伝えました。
お知り合いのお子さんで、大学受験で物理まで手が回らず、できたら教えてほしいという依頼があり、予備校の模試の範囲である力学を模試の直前に5時間ほど教えたことがあります。基本的に解く手順がしっかり身につくかどうかに注目しました。たとえ、答えの数値があっていても、解き方がまずいと直した方がいいとアドバイスしました。この勉強の終わりには、なんだか自信がついた、解けるような気がすると話していました。このなんとか解けそうだという気持ちが大切だと思います。もともと地頭が良く、のみ込みが早いお子さんだったと思います。前回の偏差値が40台であったのが60台にあがり、喜ばれていました。とにかく、本質がなんなのかを理解し、あとはなんとかなるという気持ち、自信が大切だと思います。
追記:4月にお知らせした物理のテキストも、力学の他に、熱力学・波動も出来上がってきました。