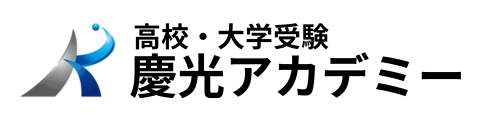中学生時代、数学が得意だったのに、高校の数学をやり始めたら成績が昔ほどよくないという経験をされている人いませんか?
中学の数学よりも高校の数学の方が難しいということも一要因でしょう。ただ、それだけではない場合もあります。むしろ、そうでないほうが多いのかもしれません。
その一つとして、中学時代に数学の得意な方は、小学校の時も得意で計算が速い、そして直観的に解き方が分かるので、頭の中でぱっぱと計算して答えまで出してしまう。そのため、解く過程などはあまりノートに残さないという場合があるのではないかと思います。人によっては、ノートをきれいにとりたいために、無駄と思える箇所は美的センスが許さず、書かない場合もあるでしょう。小学校や中学校時代では、数学が得意であったため、先生が板書したものをしっかりノートに書き写す必要がなく、その延長で高校でも板書したものをノートに書かないなどもあるかもしれません。
こういった事が、高校の数学を思ったほど点数がとりにくくしてしまっている要因の一つだと考えます。
大学入試では1問を20~30分かけて解くことはよくあることで、当然ながら直観ではどうあがいても、答えが出ませんし、頭の中だけで計算して答えを導きだすことはできません。論理的な考え方で解答を進めていく能力を試されているからです。ある条件から一つの結論が導き出され、更にその結論と他の条件から、更に別の結論が出されていくということが繰り返されることはよくあります。
ノートにしっかり自分の考えを書き、論理的に解答を進めていくということが高校数学では要求されます。単なる計算式を書くだけでは不十分です。どの条件をどのように処理し結論が出たかを記述することが大切です。書くことによって、頭の中だけで考えていたことが整理され、また記述したものを見ることで、自分の立てた考えの筋道が正しいか、ぬけがないか、客観視できます。更に、書く事によって、視覚情報から、また別のアプローチが思い浮かぶ場合もあります。このようなことを通して、問題を多角的にとらえられるようになり、難しい問題でも解ける可能性が一段と上がっていきます。
もう一つ加えると、グラフや図など書いているかがもう一つのポイントになると考えています。数式だけでなく、グラフや図を書くことで視覚的に問題のキーポイントが分かりやすくなります。個人的には、図を書いているかどうかでその子の数学の実力がどの程度かはかることがあります。
最近の大学入試の数学の問題を見ると、記述による解答が少なくっているように見えますが、論理的な思考や記述は、大学や社会に出てから要求される重要な能力です。大学では卒論などの研究論文、社会にでると自分のアイデアを製品化する際、社内の人に説明し納得してもらうために、この論理的思考はとても重要です。
高校数学では、そういった準備をしていると考えるのがよいかもしれません。数学の応用問題では論理的な流れが分かるようノートにきちんと書くことをお勧めします。